はじめに:我が家に「お小遣い」はありません
我が家では、これまで子供たちに定額のお小遣いを渡したことがありません。現在、長女は高校3年生、次女は中学2年生。友達の中には毎月決まった金額をもらっている子も多いようですが、我が家のスタンスは違います。
私自身は子供の頃、年齢に応じて月に3000円から5000円ほどのお小遣いをもらっていた記憶があります。しかし、我が家では「欲しいものがあればその都度相談」という方式を取ってきました。
とはいえ、なんでも買い与えるわけではありません。TPO(時間・場所・場面)に応じて判断し、本当に必要かどうかを子供たちと一緒に考えてきました。
お金の価値観はどこで育まれるのか
私自身、お金を使うときにはかなり慎重になります。
「これは今の自分にとって必要なものか?」
「この先、十分に活用できるだろうか?」
「支払う価値が本当にあるのか?」
そんなふうに自問自答するのが私の習慣です。だからこそ、子供たちにも安易にお金を使ってほしくないという思いがありました。
では、子供にどうやって「お金の使い方」を教えればよいのか?考えた末にたどり着いたのが、「お手伝い制度」の導入でした。
我が家のお手伝い制度とは
制度の仕組みはとてもシンプル。家のお手伝いをすることで報酬がもらえるというスタイルです。お手伝いをしたら自己申告し、家族のLINEグループで報告します。
以下が実際の「お手伝い表」です。
【お手伝い表】
●お風呂洗い ⇒ 200円
●食器洗い ⇒ 200円
●食器拭き ⇒ 200円
●靴並べ ⇒ 100円
●テーブル拭き ⇒ 100円
●21時以降スマホ預かり(長女対象) ⇒ 1000円
●ご飯おかわり(次女対象) ⇒ 100円
●副菜一品 ⇒ 100円
●悪口(相手の容姿全般) ⇒ マイナス100円
目に見える変化と嬉しい副産物
制度を始めてから、長女も次女も積極的に家事に参加するようになりました。私が仕事から帰ると、玄関の靴が整然と並んでいて感動すら覚えます。以前はバラバラで、目に入るたびに気が滅入っていたものです。
それだけではありません。以前は姉妹喧嘩がたびたびありましたが、言葉遣いを気を付ける傾向が出てきました。相手を非難する言葉が減少したことで、家庭の雰囲気も少しずつ変わってきました。
お手伝い表に家事項目を多く入れたのは、「当たり前」と思ってほしくなかったからです。家のことに手を貸すのは、家族として大切な役割。そこに少しだけ報酬というスパイスを加えたに過ぎません。
小さな社会体験として
これは決して大げさではありません。「労働によって対価を得る」という仕組みを、家庭の中で経験してほしいのです。
お金は「願えば手に入るもの」ではなく、「相手を喜ばせることで得られるもの」。それを子供たち自身の体験を通じて感じてほしいのです。
おわりに:まずは一生懸命、稼いでみよう!
難しいことは抜きにして、まずは一生懸命お手伝いをして、お金を稼いでみてください。その中で「ありがたさ」や「使い方」、「無駄にしない感覚」が自然と身についてくると思います。
これが、我が家流のお金の教育の第一歩です。



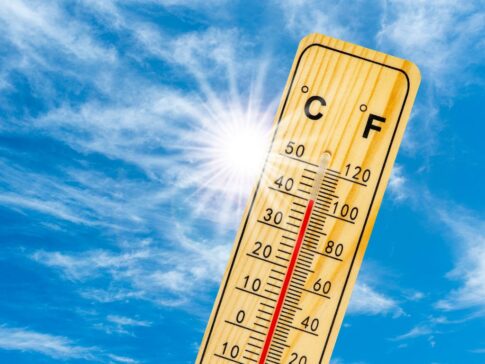







コメントを残す